富士山レーダードームが屋上に復元された姿は圧巻!日本の気象観測の歴史を学べる富士吉田の科学館。
富士山レーダードーム館は富士見バイパスを南に進み、国道138号線に合流してからも南下していくと目印となるレーダードームが顔を出します。
富士吉田市立富士山レーダードーム館は、富士吉田市立の科学館です。
そして、この三角のパネルで覆われた丸い建造物こそが台風監視のために35年間もの間、富士山頂から日本を守り続けてきた富士山レーダードームの復元なのです。富士山レーダーは、昭和40年(1965年)3月から平成11年(1999年)11月まで使われていた気象観測施設です。日本一高い富士山頂に設置された気象レーダーは、北は北海道南部、南は九州東部までの空の様子を知ることができ、いちはやく台風を察知し、天気予報や災害防止に役立ちました。
このように35年にわたり台風を観測してきた気象レーダーでしたが、その役割を気象衛星や新気象レーダーに譲ることになりました。

建物の入り口まで来ました。この階段を登るとレドーム(気象レーダーのアンテナを覆う、薄くて丈夫な建物)を間近で見ることが出来ます。入り口は向かって右側になります。

有名なポケモンでもいたのでしょうか...。思わずパシャリ。

建物の中に入ると、目に飛び込んできたのは「祝入館者100万人達成!」と書かれた横断幕。こうみると、夜のレーダードームも素敵ですね。入場料を払ってさっそく奥へ進みます。

レーダードームの三角のパネル(レプリカ)が一つだけ置いてありました。想像以上に大きい!
館内ではグラフィックパネルや寒さ体験コーナー、映像シアターなどがあり、富士山レーダーを完成させるまでの歴史やそれに至った背景まで、こと細かく説明しています。展示を通して気象観測の大切さを学ぶことが出来ます。


富士山レーダーはNHK番組の「プロジェクトX」の第一回放送で取り上げられました。
こちらのシアターでは番組で紹介しきれなかったドキュメント「世界最大のレーダー建設~富士山頂9000人のドラマ~」が上映されていました。。約50分間の上映ですが、レーダー建設への先人たちの熱意が胸に響きあっという間に時間は過ぎていきました。

二階には、5月の山頂の気温(-8℃)と風(風速13m)を体験できるコーナーがあります。防寒着の貸出もありましたが、息が出来ないほど風が強く、凍えるほど寒かったです。当時建設に関わっていた人たちはこんなにも過酷な状況下でプロジェクトを進めていったのかと、ただただ驚きを隠せませんでした。
その他にも実際に使用していた観測機器を使って気象観測を模擬体験できるコーナーもありました。

三階にはこの建物のメインともいえるレーダードームの内部(実物)を見学することが出来ます。壁には「頭上をご覧ください。」の文字が。

見上げるとクルクルと回転している直径5メートルの巨大なレーダーが!観測当時と同じ速度で回転していて、35年間も富士山頂で気象レーダーを守ってきた135枚のパネルは長い歴史を感じさせてくれました。
無謀とも言える富士山頂へのレーダードームの設置。なぜそこまでする必要があったのか。
1959年、9月22日に発生した台風15号(伊勢湾台風)は、死者・行方不明者が5千人以上という未曾有の大被害をもたらします。日本本土に近づく恐れのある台風の位置を早期に探知することが社会的急務となり、富士山レーダー設置のきっかけとなりました。
設置場所は全方向に渡ってレーダーの電波が山岳で遮られない場所。よって、高いところに気象レーダーを造れば、地形に妨害されず、遠くの空の状態を知ることが出来ます。より正確な天気予報を行うため、日本で一番高い富士山頂にこれまでの5倍の強さの電波が出せる世界一強力な気象レーダーの設置が計画されました。
ちなみに、当時すでに運用されていた新潟県や弥彦山や島根県三板山の山岳レーダーで用いた5.7㎝波レーダーではなく、富士山レーダーは異例の10㎝波レーダーを用いることにしました。使用するアンテナも当時標準だった直径3mのものから直径5mへと大型化されています。
1963年、本州を直撃する台風の早期発見を目的に富士山頂への気象レーダーの設置が決定します。
富士山の頂上に気象レーダーを造る…。それは夢のような構想だった。
富士山頂は一年の多くを雪や氷によって閉ざされ風が強い厳しい環境です。今でこそ登山道はきれいに整備されていますが、当時は不十分で極めて危険でした。このような場所に世界でも例のない気象レーダーを建設するため、観測機器の開発や資材の運搬計画、レーダー塔や観測施設の建物の設計には多くの困難が伴いました。
富士山レーダーの建設は1963年6月から始まりました。山頂は厳しい気象状況により年間およそ60日間しか工事できません。ヘリコプター4機、ブルドーザー数台が使われ、500tの資材が運ばれました。工事に携わった人は延べ9000人を超えました。山頂の空気は薄く酸素は地上の3分の2しかないため、多くの人が高山病にかかりました。普通の工事ではありえないことが次々と起こりますが、翌年は天気にも恵まれ昭和39年(1964年)9月、世界で一番高い場所に、世界一強力な電波を発射できる気象レーダーが完成したのです。
富士山頂から展示施設へ。
35年にわたって「台風の砦」となって日本を守ってきた富士山レーダーも、その役割をより広い範囲を見張ることのできる長野県車山と静岡県牧之に造られた新気象レーダーに引き継がれました。
多くの人々によって造られ、運営されてきた富士山レーダーは、日本の気象観測の象徴ともいえる施設です。気象観測の大切さを広く知ってもらうために富士山の麓の富士吉田市が復元し、ここで長く展示されることになったのです。

電気屋電子機器に関する国際的な学会IEEEによって富士山レーダーは、世界的にも類のない独創的な観測施設として、平成12年(2000年)3月にIEEEマイルストーンとして認定・表彰されました。日本では八木アンテナに続く2例目の快挙となりました。
まとめ
富士山レーダードーム館はいかがでしたでしょうか。私たちは普段当たり前のようにテレビなどを通して天気予報を見ていますが、技術者やそれに関わる全ての人たちによって出来ているということを忘れてはいけません。
35年間、日本を台風から守るために働いてきたレーダーは、これからも気象観測の大切さを伝えるためにここで回り続けるのです。
店舗情報
| 営業時間 | AM9時30分~PM5時30分 ※入場はPM5時まで |
| 入場料 | 大人600円 小中高生400円 |
| 定休日 | 火曜日 ※8月は無休 |
| 電話番号 | 0555-20-0223 |
| 住所 | 山梨県富士吉田市新屋1936-1 |
| アクセス | 中央自動車道河口湖インターより約4㎞・国道138号線沿 |
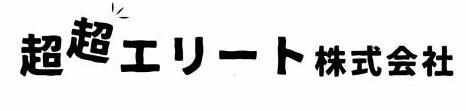

















吉田のうどんのお供すりだねの通販はこちらです。